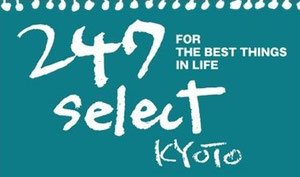歳時記2019
OCT-NOV 2019

京都には「一見さんお断り」で知られるように、しかるべき紹介が無ければ訪れることができない場所や店が多々あった。京都人は、そこに入れる事を秘密にすることが上手と言われるが、それは特権を自己満足してほくそ笑むというよりは、紹介してくれた人、受け入れてくれた人への恩義を感じて、その繋がりを大切にしたいからだと思っている。SNSの隆盛と、施設や店の維持のために、その敷居はずいぶん低くなった。いや、もはや、そういう存在は極少になったと言っていい。そういうスペシャルな場所を残して欲しいと思う一方で、維持していかねば消えていくという恐れを抱く。市街のど真ん中にある廣誠院は個人所有。どうしても残したい。維持に協力したい。けれど、多くの人に知られたくない。そういうジレンマがうずまく、秘地。
AUG-SEP 2019

江戸時代に生まれた5つの式日の最後である「重陽の節句」は別名、菊の節句とも言われる。日本の国花である菊は、平安時代には宮中の貴族に愛でられ、長寿祈願に使ったりされていた。菊にまつわる食事や文様、絵画などを組み合わせて命の尊さを願う「菊尽くし」は、今も伝わる風習だ。北山の京都府立植物園で毎年開かれる「菊花展」(2019年は10月20日〜)では、大菊、小菊、古典菊など、珍しい約1000本の菊が展示される。それは見事な光景で、菊に思いを馳せた多くの人達の思いが、花びらの奥から湧き上がるようだ。
JUL-AUG 2019

祇園祭の鉾建ての数日、四条烏丸あたりを夜、人通りが無くなる頃に歩くのが好きだ。街のあちこちから聞こえる祇園囃子の鐘や笛の音色も止んで、浮き浮きとした気分も薄らぐ、ほんの短い時間。毎年同じことが同じように繰り返される。それぞれの役割を担ったプロが淡々と祭りを形作る。どうしてこの仕事を選んだのだろう。どうやって担い手をみつけだしてくるのだろう。伝統を支える技術の継承は、確実に難しくなってきている。素材と作り手が減り、粽の数を減らした鉾もあるそうだ。長い年月の間にゆるやかに下った坂は、再び上れるのだろうか。
MAY-JUN 2019

東山・永観堂の青モミジ。秋の紅葉の季節には溢れんばかりの人で前に進むのも一苦労するのだが、この季節は人影もまばらだ。初夏というほどの暑さでもなく、しかし、風はぬるい。輝く陽が重なり合う葉から漏れ落ちて、いたるところに影絵のような模様を作る。色づく前の若いモミジは、うねるようにひろがり、すがすがしく身を囲んでくれる。ああ、もう1年の半分が過ぎた。10年前も、ほぼ変わらぬ風景なのに、どうして今は少しばかりセンチメンタルない分で歩くのだろう。あの時は、こんなに世間が混とんとしていなかったからか。年を重ねて、青モミジの勢いの迫りが判ってきたんだろうか。
APR-MAY 2019

元号が変わっても、巡る季節や川の流れは変わらず。戦火を逃れた京都は町家など古い建物がひしめいて、上から見ると美しいとは言い難い。しかしながら、その雑然と入り組んだ様子こそが、京都が開発を規制してきた歴史の証。薫風と共に鴨川沿いに床が建てられる。木組みだけのオープンエア席は狭くて暑く、ぞろぞろと鴨川沿いを歩く人が多くて騒がしい。にもかかわらず、床でのご飯食べはとても人気がある。なぜって、それは、昔と変わらないから。うちわであおぐ客の間を縫うように料理を運ぶ店の人の姿、風で乱れる髪、舞妓がふと見せる暑さにあがなう小さな疲労の表情…。鴨川の流れと同じように、変わらないことが、安心であり、価値があるのだ。
MAR-APR 2019

ああ、桜。こんなにも心躍り、そして切ない花は、無い。出会いや別れの傍にいて、短く咲き誇り、そしてハラハラと散る。神様、大切な人を桜咲く季節に逝かせないでください。季節の巡りを失った悲しみと共に過ごしたくないから。西行は「願わくば花の下にて春死なん、その如月の望月のころ」と詠った。この歌の時代にも、今と同じ姿で桜は咲いていた。惜別、慈しみ、希望、尊厳。凛凛と咲く桜に、心震わせる。
FEB-MAR 2019

京都・長岡京市の菅原道真公縁の神社、長岡天満宮は梅園を有し、境内のあちこちに梅の木がある。中でも正面の鳥居から池の中央に続く細い参道に、覆いかぶさるように咲く1本の白梅。訪れる人が、季節の巡りを迎えられたことに感謝しながら立ち止まって見上げていた見事な古木だった。何十年もの間、人々の心の小さな支えとなっていた、この白梅の木が昨年の台風で折れてしまった。形あるものは崩れ、永遠に続くものなど何もない。そうわかってはいるけれど、この傷みを、心の大きな痛みにしている人が、きっといるだろう。自分だって、チリチリと切なくなったから。低く少なくなった枝の先に花が咲いた。こんなになっても薫りたつ。どうか、悲しみが希望に変わりますように。もうすぐ雨が降るだろう。
JAN - FEB 2019

1月7日に一年の無病息災を祈っていただく七草粥。枕草子にも描かれているので(ただし秋の七草の粥)、すでに平安時代には存在した。江戸時代には五節句のうちの一つに数えられるようになったが、日本で生まれたものではなく、中国の七種菜羹がもとになっている。七種類の若葉を入れた温かい汁物を食べて出世をも願うというのがいかにも中国的。日本で「若菜の節(せち)」と呼ばれる由縁でもある。伏見桃山の「御香宮神社」では江戸時代から続く七草を神前に供える「七種神事」にちなみ、七草粥がふるまわれる。新しい年。厳しさも楽しさもある道がうねる山登り。前を向いて歩き始めるしか、ない。

 For Wonderful life
For Wonderful life